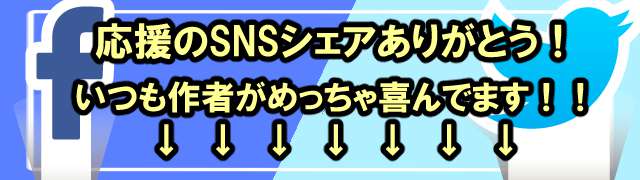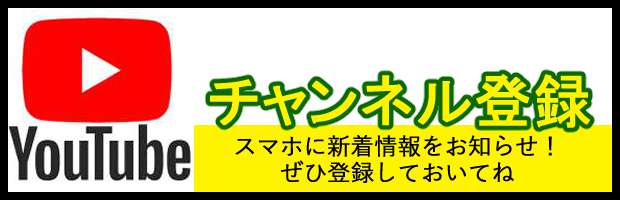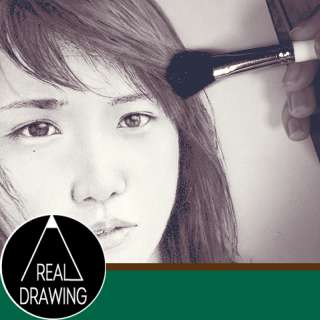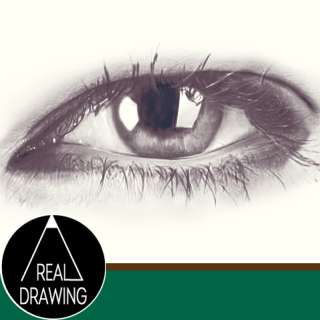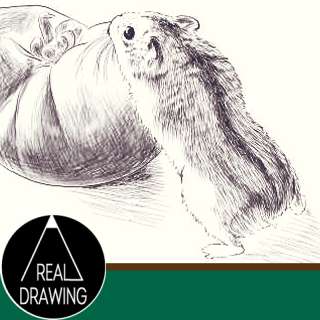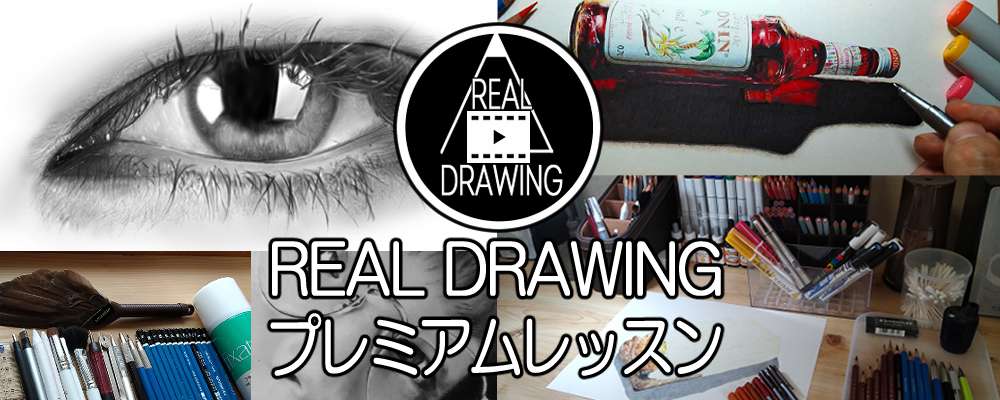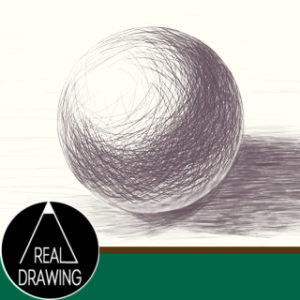初心者必見!リアル絵が上達するぬり絵
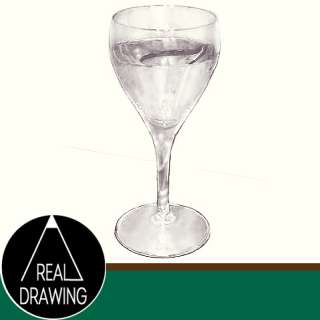
この記事でわかる絵のコツ
・この記事では、
✅リアル絵が上達する練習用のぬり絵
を用意しました。
上達する理由もあわせて、やり方を解説
したので、ぜひ体験してみてください。
目次
☑なぜ、ぬり絵がリアル絵の練習になるのか?
・モノをスケッチする力
・影の輪郭を捉える力、影の濃淡を判断する力
☑リアル絵をぬり絵で体験しよう!
・ダウンロードはこちらから
・用意するもの
・ぬり絵のやり方
☑さいごに
なぜ、ぬり絵がリアル絵の練習になるのか?
・リアル絵の書き方を考えると、
必要なスキルは大きく
✅ モノをスケッチする力
✅ 影の輪郭を捉える力
✅ 影の濃淡を判断する力
の3つと、
✅ ぬり絵をキレイに塗る力
なんです。
・これっては言いかえると、
最初の3つさえできれば、
リアル絵は誰でも描ける
ってことなんです。
・そこで、このぬり絵では
✅ 最初の3つはぬり絵で用意します
✅ リアル絵を塗って完成させる
おいしいとこだけ体験しよう!
というわけです。
■モノをスケッチする力
・「モノをスケッチする力」とは、
■スケッチが上手に描けるか
↓
■形を分析して、理論的に書き写す
力があるか?
ということです。
・スケッチが上手くなるコツについては、
別記事で書いているので、そちらも
参考にしてくださいね。
■ラテアートのコーヒーカップの描き方
※簡単なスケッチ練習ができます。
■絵が上手くなるスケッチのコツ
-スプーンを描く
※モノの形をどうやって書き写せば
いいのか、詳しく説明しています。
■影の輪郭をとらえる力
■影の濃淡を判断する力
・ふつう、影の濃淡に境界線なんて無い
ですよね。
・でも、リアル絵を描くときの手順は、
■HB,B,2B,3B…
という感じで、段階的に影をつける
■最後にティッシュとかで、影の段差
の部分をボカして、段階的になってた
影をなめらかにする。
という手順を踏むことになります。
・つまり、影のつき具合をみて
あぁ、ここらへんで、影が1ランク
暗くなってるな
みたいに、影の輪郭をとらえる力が必要
となるんです。
・実際は、こんなイメージですね。↓

・この
「影の輪郭のとらえ方」
について、具体的には別記事で書いて
いるので、参考にしてくださいね。
■リアル絵の影の描き方(基本編)
-影は階層で描ける
■リアル絵の影の描き方(応用編)
-影は階層で描ける
リアル絵をぬり絵で体験しよう!
■ダウンロードはこちらから
・以下のリンクから
✔ ぬり絵
✔ 凡例
のpdfファイルをダウンロードしてください。
・ぬり方の説明は、
✔ テキスト版(この記事の後半にあります)
✔ 動画版
のどちらも同じ内容です。


■用意するもの
✔ 鉛筆 または シャープペン(1本)
✔ 消しゴム
✔ ティッシュ
■ぬり絵のやり方
・「ぬり絵」と「凡例」をダウンロードして
印刷してください。
・「凡例」はこのように色分けされています。
これを見て、位置を確認しながら塗って
いきます。
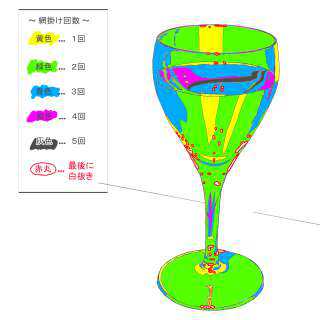
■手順1
・まずは、全体をたて線で網掛けします。



✔ あまり筆圧をかけないように、鉛筆を
少しだけ寝かせて書いてください。
✔ 面積が広い部分は、短い線で少しずつ
網掛けしてもらえればOKです。
■手順2
・斜線で2回目の網掛けをします。
・黄色の部分以外、つまり緑、青、紫、灰色
の部分に網掛けしてください。


■手順3
・手順2と逆向きの斜線で3回目の網掛け
をします。
・青、紫、灰色の部分に網掛けします。


■手順4
・横線で4回目の網掛けをします。
・紫、灰色の部分に網掛けしてください。


■手順5
・最後、5回目の網掛けをします。
網掛けの向きはどの方向でもOKです。
・灰色の部分に網掛けします。


■手順6
・ティッシュを指に巻き、全体をこすって
ぼかします。
網掛けの線が目立たなくなるくらいで
OKです。
力を入れ過ぎるとムラになるので、
やさしく撫でる感じでこすりましょう。
■手順7
・仕上げに光を入れます。
消しゴムの角を使って、凡例を見ながら
赤丸の部分を白く抜いてください。
光が反射して光っているように見える
ようになったら、完成です。

さいごに
・いかがだったでしょう?
・慣れてきたら、今度は下描きのグラスの
絵から、自分で描いてみてください。
すると、影の境い目の線がなくなるので、
こんな感じで描けるようになります。
ぜひ、チャレンジしてみてくださいね!

最後まで読んでいただき
ありがとうございました
こちらの記事もオススメ
作者の「次もいい記事を書くぞ!スイッチ」はコチラ!
↓↓↓
この下のSNSボタンをポチッと押すと
お友達にこの記事を紹介をできます