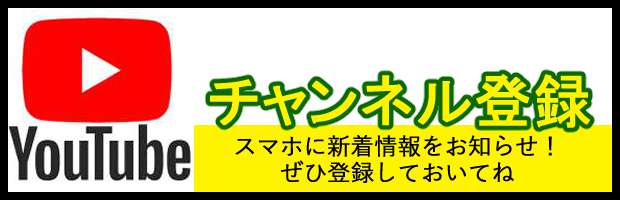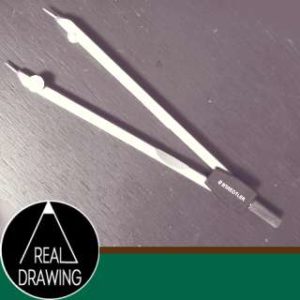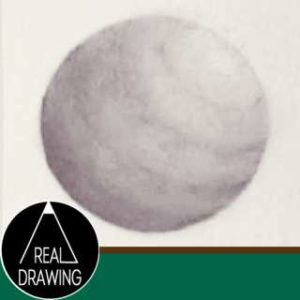さよなら塗りムラ|筆圧を一定にする4つのポイント
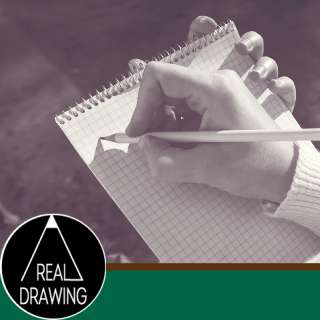
この記事でわかる絵のコツ
・リアルな絵の描き方で多い悩みの
ひとつとして、
広い面積をキレイに塗りたいのに
塗りムラになってしまう
ということをよく聞きます。
⇒じつは、この「塗りムラ」は、
4つのポイントを実践することで
劇的に改善
するんです。
・この記事では、
✅筆圧を一定にすれば塗りムラ
がなくなるということ
✅筆圧を一定にするための
4つのポイント
について解説するので、
塗りムラで困っている
という人は、ぜひ読んでみてください。
目次
✅筆圧一定は、リアル絵を描く上で
欠かせないテクニックです
✅筆圧を一定にして塗る4つのポイント
✅ポイント1:鉛筆の角度
✅ポイント2:鉛筆を紙に押し付ける力
✅ポイント3:鉛筆を動かすスピード
✅ポイント4:鉛筆の芯先のとがり具合
✅さいごに
筆圧一定は、リアル絵を描く上で欠かせないテクニックです
・リアル絵では、10H ~ 10B のいろいろな
濃さの鉛筆を使い分けることで、濃淡を
コントロールします。
逆にいうと、例えば2Bの鉛筆で塗っている
ときは、全て2Bの濃さで一定にさせたい
わけですね。
塗っている途中で筆圧が変化してしまうと
自分の思い通りに塗れないうえに、塗りムラ
になってしまうというわけです。
筆圧を一定にして塗る4つのポイント
■塗りムラは、筆圧を一定にするとなくなります。
・たとえば、スベスベの肌を塗ろうとしたときに、
筆圧が変化すると「塗りムラ」となってしまい、
肌荒れみたいな絵になってしまいます。
・筆圧変化の原因は、次の4つです。
✅ 鉛筆の角度
✅ 鉛筆を紙に押し付ける力
✅ 鉛筆を動かすスピード
✅ 鉛筆の芯先のとがり具合
この4つについて、お話します。
ポイント1:鉛筆の角度
・まずは「鉛筆の角度」です。
✅圧力は接地面積が小さければ小さいほど
力は一点に集中します。
■ 例えば、この図のように
10の力が加わったとき、接地面積が1で
あれば、その1点に力は10かかります。
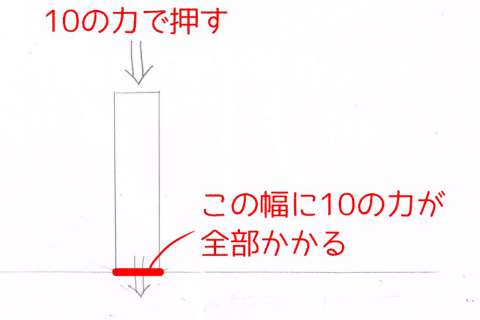
筆圧を一定にする方法1
ーーーーーーーーー+---------+
■ これが
接地面積が10倍になれば
同じ10の力が加わったとしても、
力は1づつに分散されます。
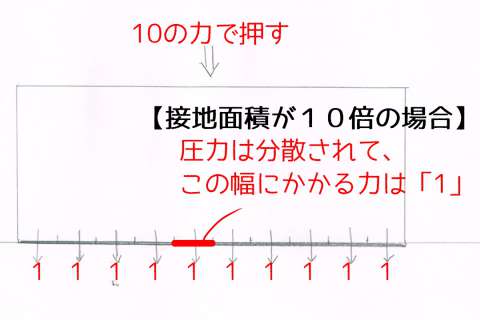
筆圧を一定にする方法2
✅これを、鉛筆の角度で考えると次のようになります。
■鉛筆を立てる
芯の先しか紙に当たらないので、
筆圧は高くなる = 色が濃くなる
■鉛筆を寝かせる
芯の広い面が紙に当たるので、
筆圧は低くなる = 色がうすくなる
✅通常、広い面積を塗る場合は、下の写真のように
鉛筆を寝かせて塗っていきますよね。
このとき、同じ筆圧で塗っていく場合は、
常に鉛筆の寝かせ具合を一定に保つ
ということを意識することが重要なのです。

ポイント2:鉛筆を紙に押し付ける力
✅当たり前ですが、
押し付ける力が変われば筆圧は変わる
に決まってますよね。
でも、ずっと同じ強さで鉛筆を動かし続ける
のは、非常に難しいです。
✅これを解決する方法は、
鉛筆を指で無理に紙に押し付けない
ということです。
✅もう一度、この写真の持ち方を見てください。

これは、
✔ 人差し指と中指に鉛筆をのせる
✔ 親指は支えるだけ
という持ち方をしています。
この持ち方であれば、 鉛筆の重さだけで
塗ることができます。
✖ 親指で上から押さえつけないよう注意!
鉛筆の重さだけで塗っていけば、
かなり一定の筆圧で塗ることができます。
ポイント3:鉛筆を動かすスピード
・次に「鉛筆を動かすスピード」です。
✅動かすスピードが変化すれば、筆圧も
変わってきてムラができる
⇒常に一定のリズムで鉛筆を動かすことを意識します。
✅鉛筆が往復するときの
✔ 動き出す部分
✔ 止まる部分
は重要です。
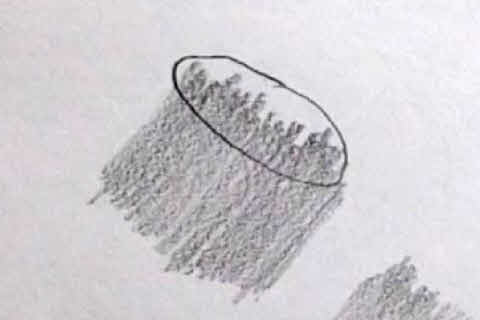
筆圧を一定にする方法3
この部分が一番無意識に力が入りやすく、
色が濃くなりやすい部分です。
✅このムラを無くす方法は、
鉛筆を早く動かしすぎない
ということです。
特にHBより硬い鉛筆を使う時は、塗りムラ
の修正が難しいので、丁寧に鉛筆を動かす
ようにしてください。
ポイント4:鉛筆の芯先のとがり具合
・最後に「鉛筆の芯先のとがり具合」です。
✅鉛筆を使うと、芯先は徐々に丸くなります。
尖っていた鉛筆が丸くなる
⇒ 芯の接地面積が増える
⇒ 筆圧が下がる
⇒ 筆圧が変化するので塗りムラになる
こんな流れになります。
ですので、鉛筆の芯先のとがり具合には
常に注意しましょう。
✅鉛筆を寝かせて使っているとき。。
定期的に鉛筆を少し回転
させながら使います。
使いづらくなってきたら鉛筆を削りましょう。
✅鉛筆を立てて使っているとき。。
回転させても意味ないです。
丸くなってきたなと思ったら
早めに削りましょう。
さいごに
・この4つのポイントに注意して描くと
仕上がりがかなり変わります。
・また、鉛筆の筆圧は持ち方によっても
大きくかわります。
リアル絵・デッサンの鉛筆の持ち方
こちらの記事を読まれていない方は、
合わせて読んでいただくと、
より深く理解できるかと思います。